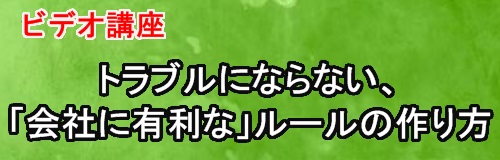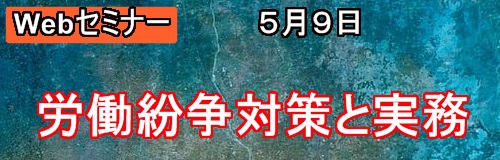マックス・ヴェーバー「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」。――難しいけれど、面白い名著だ。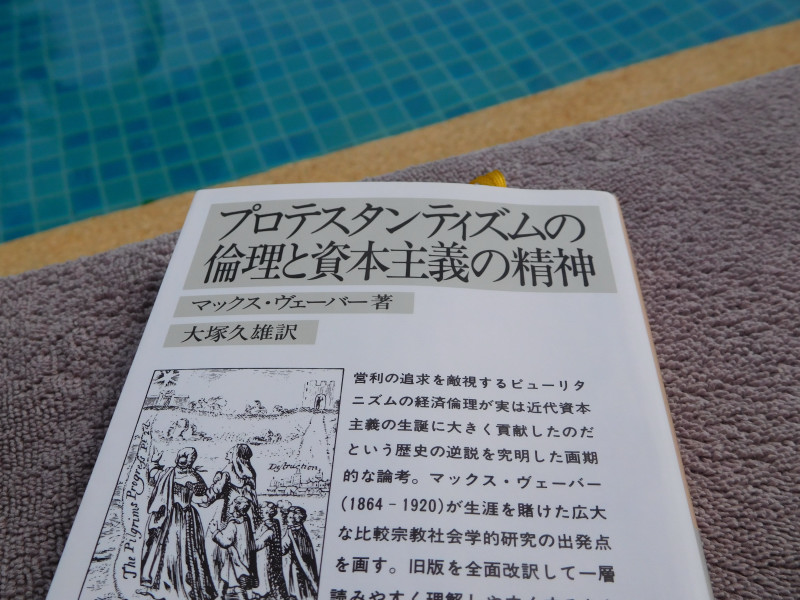
年末タイのビーチで読み始めて、丸半月以上かけてやっと読了。特に第2章第1節、150頁にわたる「宗教的諸基盤」の叙述。宗教史の予備知識がない私にとって大きな難関だった。しかし、読み終えてみると、いろんな疑問が解けて、近代資本主義を裏付ける、宗教に由来する精神的な部分については概ね枠組み的に理解できた。
16世紀後半、イギリス国教会内部から生じたプロテスタントの一派ピューリタン(清教徒)の思想といえば、禁欲、利益追求の禁止。一見資本主義そのものと根本的な対立をなす思想だが、なぜ近代資本主義の精神と関係付けられたか。その疑問がほぼ解けた。
要するに、労働は禁欲の手段である。
人間はブラブラしていると、欲望に駆られてろくなことをしない。だから、労働しろと。労働していれば、そういう悪いことを考えなくなり、しなくなる。労働をもって禁欲する。つまり行動的禁欲である。禁欲は何も修道院の中に限られたものではない。世俗の中でも職業労働によって実現できるものだ。
天職の概念を打ち出す。
では、どのような職業労働につくか。社会における分業や職業編制は神の計画によるものだ。人々がこの秩序に編入されるのは自然的な原因によるものもあれば、偶然的なものもある。人間は神から天職を与えられ、職業労働はその種類にかかわらずすべて尊いものだ。したがって、個々人がこのような「天職」に付与された労働義務を忠実に果たさなければならない。
そこから、アダム・スミスの有名な分業讃美論との関連性を想起する。
職業の特化は、労働者のスキル(熟練性)を可能にするため、労働の量的ならびに質的向上をもたらす。したがって公共的利益・福祉の向上につながる。功利主義的な要素が見られる。とはいっても、全体的福祉、非人格的な有用性であるが故に、現世や被造物の栄化にではなく、神の栄光につながるのである。
天職である職業義務の履行は、道徳上許されているだけでなく、まさに神に命令されているのだ。その労働義務を履行しない者は罰せられる。つまり、働かざる者食うべからず。
そこで、弱者に施しを与えて良いかというと、施しは慈善にあらず。一見キリスト教精神に基づく「相互扶助の原則」に反しているかのように見えても、本質を吟味すれば、納得できる。「市場に任せよ」といった経済的自由主義の原型から形成した新たな規範としての地位を獲得し、「自助の原則」に基づく市場社会の成就につながった。
18世紀ドイツの宗教指導者ツィンツェンドルフがいう。「人は生きるために労働するだけでなく、労働するために生きているのだ」。まさにその通りだ。勤労は体力の自然的目的であるとともに、倫理的目的でもある。神にもっとも奉仕しその栄誉となるものは労働という行為である。
生産性の向上を伴う天職である職業労働義務の履行によって、自然に富が蓄積される。このような利益追求行為が教義に反するのではないかというと、まったく違う。
自他に害を与えず、法律を守ったうえで、より多くの利益を得る機会があれば、その機会を利用すべきだ。逆に利益の少ない選択肢を選ぶほうが、天職への召命(コーリング)に逆らうことになる。神のために労働し、富裕になるというのは良いことなのだ。
単純な富の追求は富であるが、労働に伴う富の保有はそうではない。富そのものの罪よりも、富の所有の上で休息すること、富の享楽によって怠惰や肉欲につながることが罪だ。富裕というだけでそれが労働をやめる理由にはならない。貧者と同じように労働しなければならない。
金持ちになっても贅沢や浪費をしてはならない。さらに労働しなければならない。生活に必要な支出以外の消費はご法度だ。さらに、金銭的消費を規制する禁欲以外に、時間の浪費も規制対象とされる。
「時間は金なり」の原型となるものは、時間の無上の価値を表している。人生の時間は、自分の使命を確実にするためには、限りなく短くかつ貴重だ。時間の損失は、交際や無益なおしゃべりや贅沢によるだけでなく、必要以上の睡眠によるものである。道徳上絶対に時間の無駄を排斥しなければならない。
過剰な消費をせず、無駄をなくし、睡眠時間まで削って、恒常的な労働を積み上げた結果は、富の増加にほかならない。資本が資本を生み、更なる大きな富を生み出す。消費されない富が再投資に回され、際限なく膨大な富を積み増していく。というまさに近代資本主義の姿が現れたのである。
という宗教を基盤とする「資本主義の精神」は、富の増加とともに徐々にフェードアウトする。天職の職業労働よりも、現実の世界ではキリスト教を含めて利益追求が目的化されてきた。その変質を引き起こしたものは何であろう。それは人間の欲にほかならない。要するにそもそも欲があっての禁欲だった。それが宗教という倫理的規制が機能する世界ならまだしも、それが弛緩した現今の自由主義の世界ではもはや、制御する術がない。
16世紀や17世紀当時のピューリタンたちがいま、もし生きていたら、いまの資本主義社会を俯瞰してどう言うのだろうか。「われわれが当時意図していたものではありません」と懸命に弁解するだろう。彼たちの間違いではない。歴史はすべて必然的帰結である。