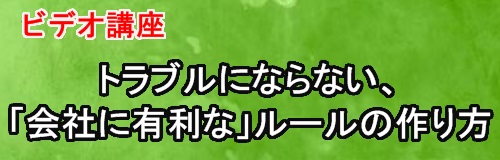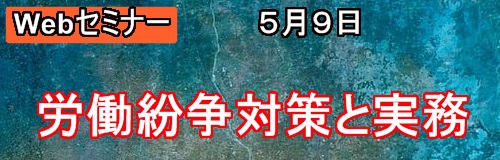<前回>
(敬称略)
東京近辺の地上げはもちろんのこと、H不動産会社は、いよいよ中国・上海にも目を向けようとした。
目指すところは、あの上海の古北地区の開発だった。
89年当時の上海虹橋空港に、私は、意気揚々のH不動産・黒田社長と降り立った。当時の虹橋空港は、いまのターミナルBの原形しかなく、国内国際共用で、狭い割にはガラガラだった。空港を出れば、灰色の中国がそこにあった。人々の着装は、灰色かブルー系の人民服が中心、女性のスカート姿もほとんどなかった。
私たち一行のスーツ、ネクタイ姿は、街中でひと際人目を引き、どこに行ってもじろじろにらみつけられる。「あっ、外人だ!」
早速、開発区政府が用意してくれたバンに乗り込むと、一路、信号がほとんど無い状態で、あっという間に、古北到着。はっきり言って、当時の古北は、一言でいうと、紛れも無い本物の農村だった。因みに、あのときの上海市街地の西側の境界線は、概ね、あの「揚子江ホテル」(いまは、マリオット系のルネッサンスホテル)あたりにあった。揚子江ホテル以西の界隈は、ほとんど田んぼだった。
雨止んだ直後の古北は、足元が悪い。政府の役人たちが、親切にもゴム製の長靴を用意してくれた。履き替えると、すぐに現場視察。公式通訳はもう一人、中国人女性がいたので、私の主な仕事は、黒田社長のための個人通訳とアドバイザーだった。
目の前に広げられた古北地区開発のマスタープランは、ほぼ今の街並みをそのまま描いたものだった。あの半円系の道路も、図面に載っていたことは、いまでも鮮明に記憶している。ちょうど、あのとき、泥沼の田んぼに足を踏み入れた場所は、今のカルフール辺りだったかなと思う。
「何とか、資金を集めたところで、早急な着工を希望する」、開発区の担当役人が興奮している。視察を終えた私たち一行は、上海静安ヒルトンホテルにチェックインして、即会議に入る。
合弁の話はとんとん拍子で進む。ほぼ口頭合意にこぎつけたところで、盛大な歓迎宴会が催された。これからは、月一回、上海に黒田社長と出張することになる。
食後、ヒルトン39階のバーでカクテルを飲みながら、当時極めて珍しいフィリピン人バンドの生演奏を楽しんだ。大きなガラス張りの外は、暗い上海の夜。ぽつんぽつんと飲み屋のネオン以外は、何もない。雨上がりの夜空に、星が笑っているだけだった。
寂しい街だ。私にとって、六本木の街の明かりがこれほど懐かしくなるときはなかった。
三次会は、街に繰り出し、上海賓館の近くにある怪しいバーに入る。暗いボックス席が3つほどあって、小姐とお話をしながらのバータイムだった。不味いジョニーウォーカーの水割り、湿気たピーナッツのつまみ、カラフルの豆電球、ソファーの破れた皮から、顔を覗かせる中身のスポンジが湿っぽく、肌に触れると全身に痙攣が走る。
「キスしても良いよ、チップは30元で良い」、隣の小姐が急に色っぽい笑顔を見せる。社会主義国家の中国というイメージは、このとき、一瞬に消え去った、「次、上海に何時来るの、日本の口紅買ってきてくれる?」
隣のボックスにいる黒田社長は、言葉は大丈夫かなと思いきや、小姐と熱烈なキスを交わしているのではないか・・・なるほど、万国の共通語は凄い!