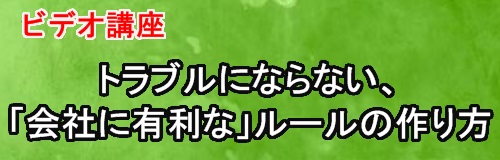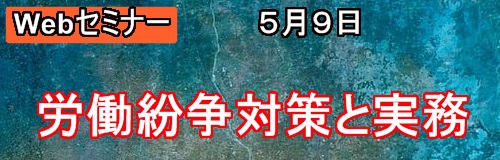<前回>
(敬称略)
古田部長は、決して悪人ではない。仕事ができる有能な部長だった。彼の業績はロイターの中でも優秀な方で、仕事面でいえば私は彼をとても尊敬している。その反面、自信の持ちすぎで権力支配欲の塊に変身したのか、論理的にそれを結論付けすることはできないが、「古田王国」の存在だけは、否定できないものだ。
「封建王国」といえども、それも組織形態の一つ。会社に対し、NP部という部門組織として悪くない業績を上げていれば、その組織の「自治権」を会社が保障する。2000年初頭なら、いまほどパワーハラスメントなどが問題になっているわけでもなく、「十か条」こそ経営陣に「う~ん」と言わせたのかもしれないが、全体的に決してこの部署を問題視していたとは思えない。おそらく「古田王国」に対し、公に派手なクレームをつけたのは、私が初めてだったのではないかと思う。集団現象ではなく、あくまでも個人単位の問題であれば、それは問題ではないというふうに理解しても納得するだろう。
しかし、私という個人レベルになると、話が違ってくる。
ロイターは、典型的な欧米型企業である。自由な社風に引かれて私が入社した。仕事の業績に大変厳しい会社で、パフォーマンスに基づいた人事考課と待遇設定はドライであり、温情人事は皆無に等しい。その代わりに、社内人間関係や社内営業に余計な気を配ることがないのが、私にとって一番の魅力だった。上海時代も香港時代も、責任こそ重いものの、自由に仕事ができた。しかし、「古田王国」は、ロイターという会社の中の治外法権的存在だった。周りに自由に仕事をしているほかの部署の人たちを見て、何だか無性に悲しくなる。
そう、NP部は、会社の中の「飛び地」のような存在だった。飛び地の中に閉じ込められた自分は、言葉で表すことのできない孤独感と苦痛を味わっていた。
古田部長は、部の長として、部のルールを決める権力がある。それは否定できないし、また、それはそれで古田流儀のルールを非難する立場には私がない。しかし、私がその部に配属されたのは、決して自分の意思ではなかった。自分で選択する権利がなかった。だから、そのルールがどうしても嫌だったら、選択肢は三つある。
その一、服従して忍耐する。
その二、戦って、ルールを変えさせる。
その三、会社を辞める。
私は、まず選択肢その一を否定した。納得しないことを強いられ、ただただ耐えていくのが性に合わないし、貴重な人生の時間を無駄にすることは決してできないからだ。そして、選択肢その二を試みたものの、組織を前面にして自分が如何に無力だということを思い知らされた。すると、残される道は一つしかない―会社を辞めることだ。
「会社を辞める」、これは、一サラリーマンが会社に対し取れる唯一の対抗手段である。
社長直訴の書状を書き上げたとき、末筆に辞職の旨を記しておいた。