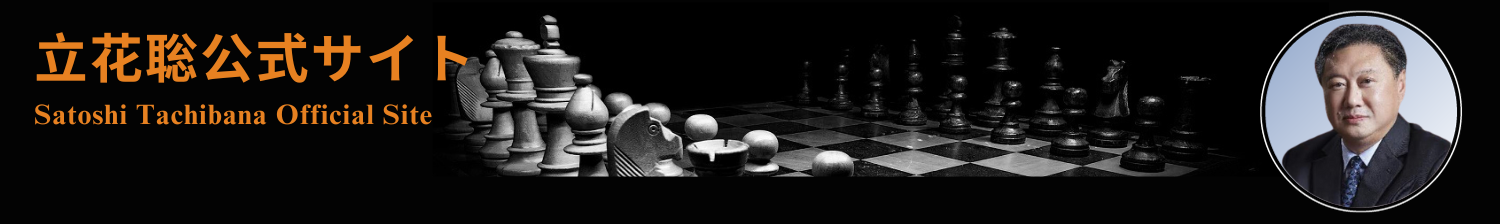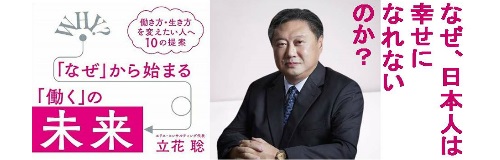「義・勇・仁・礼・誠・名誉・忠義」。これは武士道における七徳とされ、日本人の倫理観や行動様式に深く根差してきた。
しかし、これらを「真・善・美」の3つの価値基準に照らして眺めれば、その構造的な偏りが露呈する。七徳はいずれも「善」と「美」に属する道徳的・審美的要素であり、「真」に相当する要素が存在しない。
「誠」はしばしば「真」と同一視されがちだが、それはあくまで対人関係における誠実さや忠実性を意味し、客観的な事実認識や論理的真理の探究を意味する哲学的な「真」とは異質である。
この「真」の欠落こそが、日本文化における思索の弱さ、哲学的思考の不在をもたらした根因のひとつである。行動規範や人間関係の秩序を重んじるあまり、根拠や理論の整合性、つまり「何が本当に真であるか」を問い直す姿勢が歴史的に育たなかった。
結果として、現代の日本においても、論理より「空気」、事実より「気配り」、真理の追究よりも「場の美しさ」が優先される文化的傾向が色濃く残っている。
日本の衰退を語るとき、経済や外交、教育の制度論に焦点が当たりがちであるが、根本的には「真」を構造として持たない文化そのものに問いを差し向ける必要がある。武士道は今なお称賛の対象として語られることが多いが、時代が変わった今こそ、この七徳に「真」を加え、現代的思索に耐えうる倫理の再構築が求められているのである。