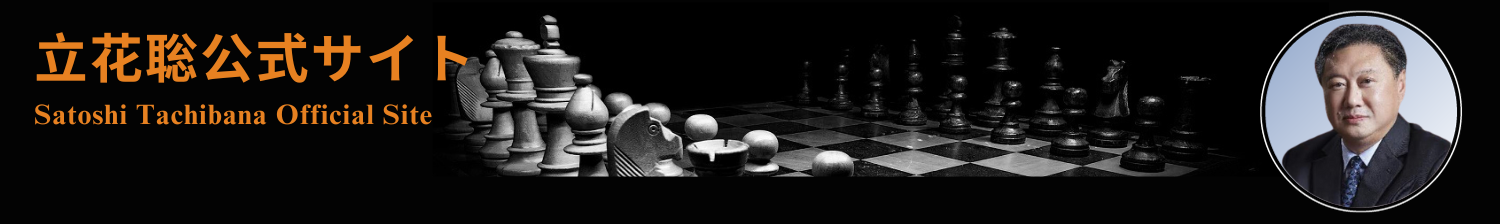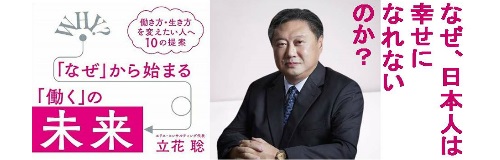2025年5月、ハナが旅立った数日後、Facebookのダッシュボードに異変が起きた。再生数が跳ね上がった。いいね、シェア、コメントも比例して増えた。プロフェッショナルダッシュボードは、感情を持たぬ機械の顔で「+325.7%」という数字を表示した。

普段は20万の再生数が、あっという間4倍強の急増で88万を超えた。何かが「届いた」のだろう。しかし、熱は長くは続かなかった。アクセスは突然潮が引くように静まり、反応は鈍くなり、やがて沈黙が訪れた。それは自然なことだった。だが私は、その静けさの背後に「何かの断絶」を感じた。
私は誰かを責めたわけではない。ただ、ハナを躾けなかったこと、飾らなかったこと、そのままの彼女を、彼女のまま見送ったことを書いた。多くの人は、犬に躾をし、衣装を着せる。愛情のかたちとして、それを日常としてきた。私はそれを否定したわけではない。だが、私の選択は、その大多数の行動とは異なる価値観を明確に示すことになった。
その結果、多くの人が自分の選択を否定された、批判されたと感じたのだろう。
すると、それまで当たり前のように「いいね」を押してくれていた友人たちが、次の投稿では無言となり、さらに次には姿を消した。私が語ったのは、選択であって批判ではない。だが、人は往々にして、自分が照らされたときに「否定された」と感じ、沈黙を選ぶ。沈黙の奥には、防衛と拒絶が同居している。
言葉には、思いがけず「篩(ふるい)」の機能がある。私の言葉は、共感を求めたものではなく、ただ事実と立場を記述しただけだった。それでも、そこに含まれた強度が、人々を選別してしまった。同調を求めていた人たちは、離れていった。それは敵意ではなく、自己保存だった。言葉の温度に耐えられなかったのだ。
共感は、同調とは違う。同調は群れを形成するが、共感は個を貫いて届く。私が残してしまったのは、共感ではなく、沈黙だったかもしれない。だが、その沈黙の向こうに、まだ読んでいる者がいる。姿は見えず、言葉もないが、スクリーンの向こう側でページをめくる音が聞こえるような感覚がある。私が語るべきは、その者に向けてだ。
これは、大勢のための文章ではない。沈黙を通過した者とだけ共有される、静かな交感の場。それが、今、私の言葉の居場所なのだ。