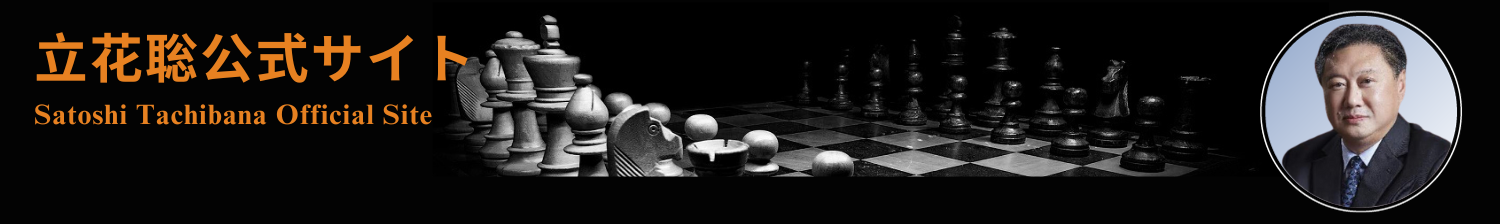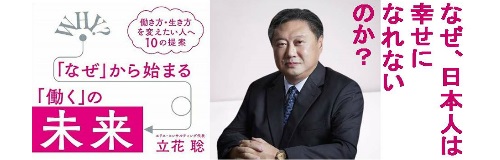「泣けました」という言葉を何度かいただいた。私の文章を読んで、涙が出たという。素直に嬉しく思う。悲しみや別れの描写が、誰かの心に触れ、感情の奥を震わせたのであれば、それは書き手にとって確かに報われる瞬間である。だが一方で、私はその反応に、わずかな引っかかりを覚えていた。泣いた——それは大切なことだが、果たしてそこで終わってしまってよいのだろうか。

情動的な共感は、読者と書き手を一瞬つなぐ。しかしそれは多くの場合、感情の波が引いたあとは元の日常に戻る「消費される共感」にとどまる。「泣ける話」として処理されることで、かえってその背後にある問いや価値観は見過ごされてしまう。私は、それを望んでいなかった。
私が本当に書きたかったのは、涙の先にあるものだ。涙が乾いたあとに、ふと立ち止まり、何かが自分の中で揺らぎ始める瞬間。ハナの姿を通じて、「自分はどう生きているのか」「どう他者と関わっているのか」を考え始めるその地点にこそ、私は言葉を届けたかったのだ。
私がハナに対して選んだ生き方——躾けない、飾らない、ありのままを尊重するという姿勢——それは単なる飼い主の方針ではない。もっと根源的な問い、「自由とは何か」「尊厳とは何か」「死とは何か」に接続していた。
人はなぜ、動物の死に心を動かされるのか。それは、動物が損得抜きに生き、死んでいくからだ。彼らの生には計算も演技もない。だからこそ、私たちはその死を前にして、自分の在り方を問われる。動物の死は、私たち自身の「倫理」を映す鏡なのだ。
「泣けた」と言ってくれた読者には感謝している。そして、そこからさらに一歩踏み込んで、自分の価値観や行動を見つめ直してくれた読者がいるなら、私はその人の中に小さな哲学が芽生えたと信じたい。
涙は、終わりではない。むしろ、そこから始まる。私の言葉の真正の受け手とは、涙のあとに問いを持ち続ける人、そしてその問いに自分で向き合おうとする人なのだ。