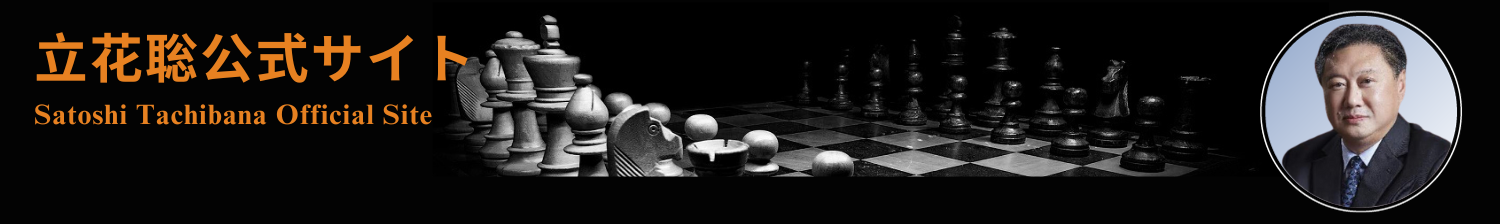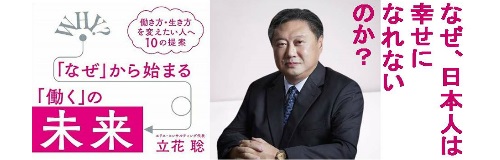「よく躾けられた犬ですね」。その言葉は、ほめ言葉であると同時に、支配の達成を告げる宣言でもある。人間が動物を含む他者を「望ましい姿」に矯正し、従わせるという構造。それは、教育、育児、訓練と名を変えつつ、実は極めて政治的な営為である。

しつけ教室とは何か。それは、動物を人間社会に「適応させる」ための訓練所である。しかし、その適応とは誰の定めた秩序への従属なのか。そこにおいて問われているのは、動物の幸福ではなく、人間の快適さと安心、自己満足である。つまり、躾とは「人間中心主義的秩序装置」に他ならない。
私たちは無意識のうちに、従順さを善、美、正義と同一視してきた。だが、それはかつて近代国家が臣民を、企業が従業員を、教師が生徒を、親が子を、あらかじめ規定された型に押し込めようとしてきた装置群と構造的に同型である。命令に従うこと、異議を唱えないこと、沈黙すること。これらは「良い子」「良い社員」「良い犬」に共通して求められる規範である。
しつけ教室での「リーダーシップ」は、実のところ「支配権の正当化」にすぎない。フーコーは、近代以降の権力はもはや王のように「上から命令して暴力的に支配する」ものではなく、人びとの内面に入り込み、彼ら自身に「自発的に」従わせるかたちで機能すると指摘した。
しつけ教室とは、犬に対して鞭や檻で強制するのではなく、「褒める」「無視する」「行動の修正を誘導する」といったポジティブに見える操作を通じて、犬自身が進んで人間の期待に応えるよう仕向ける場所である。つまり、犬は「叱られたくない」からではなく、「褒められたい」から行動を修正する。
飼い主は「強制している」と自覚することなく、従順な犬を「良い犬」として育てる。その過程で、犬は人間社会に「適応」するという名目のもと、「自由の名の下の服従」を覚える。この全体構造は、まさにフーコーが語った近代社会の統治性そのものなのである。
野良犬たちはどうだろう。彼らは命令を持たず、服従を知らない。だが、そこには明確な秩序がある。距離のとり方、目線の交わし方、吠え方、逃げ方――すべてが、相互の暗黙的了解によって構成されている。この秩序は、「命令の言語」ではなく、「共鳴の沈黙」によって築かれている。
しつけ教室をやめ、「共鳴」を通じた関係へと転じた行為は、まさにこの見えない支配の回路から一歩外に出た試みであり、哲学的には「脱・統治性」、あるいは「自由の回復」とも言えるでしょう。
私は、ハナ(ほかの愛犬も同じ)との関係において、この共鳴の可能性を感じていた。命令をやめたとき、彼女の呼吸に私の心が同調しはじめた。理解しようと努めるとき、私は初めて彼女に「教えられる者」となった。躾とは、犬を変えることでなく、人間が変わることでもあるのだ。
産業化されたしつけ教室は、従順という記号を量産する。だが、動物は記号ではない。彼らは生きている。他者としての全存在を賭して、私たちの傲慢と恐れを映し返してくる。その鏡像を見据える覚悟が、私たちにあるのか。
支配と共鳴。どちらを選ぶかは、私たちの哲学である。