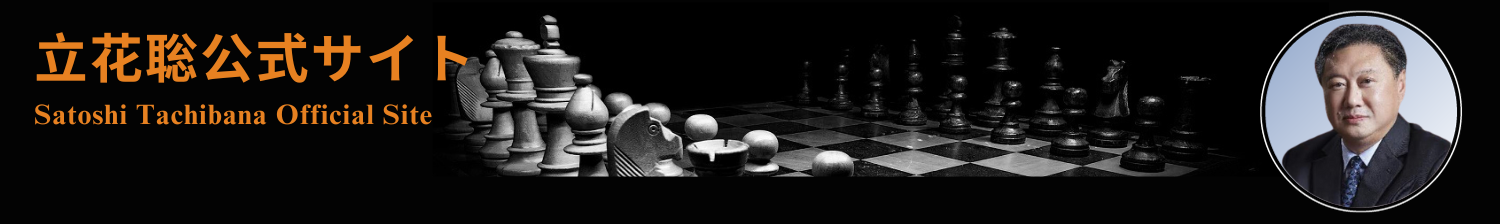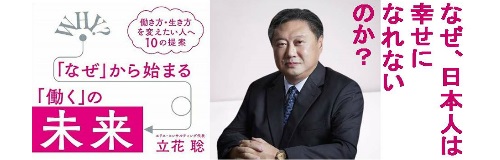「癒される」。ペットを飼う人々の共感である。
癒しは、決して否定されるべきものではない。苦しみや痛みを抱えた者が、動物の存在によって慰められ、救われるという現象は、まぎれもなく現実に存在する。事実、私自身もそうであった。ハナがいてくれたからこそ、私は幾度も心の深い谷を越えることができた。彼女の呼吸、眼差し、沈黙の温度。それらは、言語を超えて私の内部の崩壊を支えてくれた。

だが、癒しは一方通行であってよいのだろうか。人間が苦しむときにだけ都合よく寄りかかり、快復すればその存在を忘れてしまう――それがもし「癒し」の定型であるとすれば、そこには隠された搾取の構造がある。
癒しは、しばしば「受け取ること」と同一視される。すなわち、癒しの享受は受動的な消費行動として機能している。癒されたい、慰められたい、救われたい――その欲望の下で、動物の存在は「セラピー資源」として消費される危険性を孕んでいる。
問題は、癒しを否定することではない。問題は、癒しを最大化するために、相手を「制御可能な存在」として扱い始めることにある。動物が飼い主に寄り添い、従順に振る舞い、なぐさみを提供する存在として仕立てられていくプロセスに、無自覚な支配性が介在している。これは、癒しを「最大効率で」得ようとする人間の能動的な支配であり、「癒される側の暴力」である。
本来、癒された者は、その恩恵をただ享受するだけでは足りない。癒された者には、返礼の責任がある。その返礼とは、単なる感謝の言葉や記念碑的な行為ではない。真の返礼とは、癒してくれた存在への全身全霊のケアと、彼らを深く理解するための能動的学習にほかならない。
動物は、人間を成長させる鏡である。彼らは教えない。だが、彼らは映し出す。人間がいかなる存在であるのか、人間の欲望がいかに自己中心的であるのか、人間がどれほど「癒される資格」に値しない存在であるのかを、鋭く沈黙のうちに突きつけてくる。
だからこそ、癒しを受け取ったとき、私たちは立ち止まらねばならない。その癒しは誰によってもたらされたのか。その癒しの背後には、どれほどの耐え忍ぶ力と与える覚悟があったのか。そして、私たちはそれにどう応えるのか。
癒されることは、同時に問われることでもある。癒されるとは、無垢に戻ることではない。癒された者こそが、世界と他者に対して、より深い責任を持たねばならないのである。