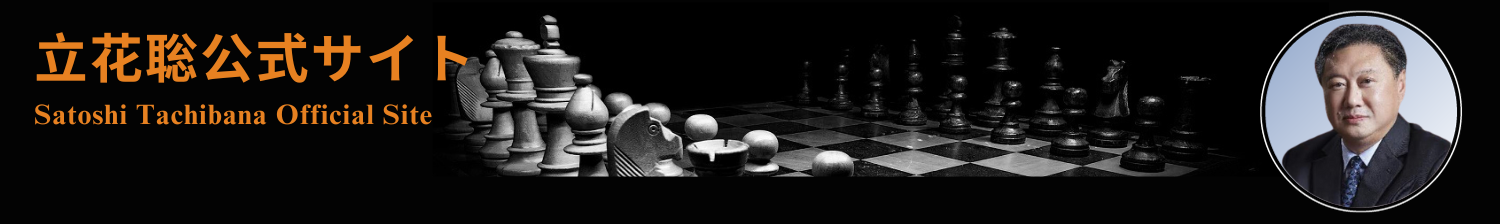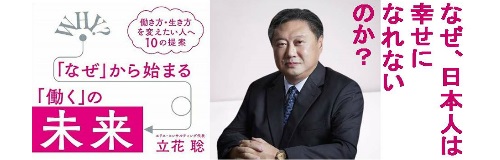「言葉にならないもの」と共にあることの孤独。
喪失の痛みは、往々にして言語を拒絶する。それは、言葉にすればするほど遠ざかっていく実感であり、説明すればするほど陳腐化する現象である。だからこそ人は、沈黙の中で痛みと共にあろうとする。しかし、周囲はそれを許さない。慰めの言葉、励ましの言葉、共感の言葉――それらは、沈黙に対する世俗の「干渉」として次々に投げ込まれる。

「比べられた」「慰められた」ではなく、「奪われた」と感じることがある。他者の「共感」という行為によって、自分の痛みが相対化され、取り上げられ、処理され、分類されていく。そこには、「理解してあげる側」という立場性がある。痛みに寄り添うふりをして、実際には他者の経験を自分の理解の枠内に回収しようとする操作――それは、まさに「共感の皮をかぶったマウンティング」である。
喪失の痛みは、それぞれに固有であり、比較や翻訳を拒む絶対的なものとして存在する。にもかかわらず、人びとは「私も経験がある」「分かるよ」という言葉で、それを一般化しようとする。だが、真の共感とは、理解することではなく、「理解できないことを理解しようと努め続けること」にあるはずである。
哲学は、この「理解できなさ」の淵に立つ営為である。だからこそ、哲学は世俗に嫌われる。癒しも解決も提供しない、問いだけを差し出す営み。それは、成果主義の時代において、最も忌避される無益さを体現している。人間関係の潤滑油にもなれず、効率的な処理にも貢献せず、ただ「なぜそれが問題なのか」を問う存在。哲学は、社会的機能性から逸脱している。
だからこそ、哲学は孤独である。だが、その孤独は敗北ではない。それは、痛みを痛みのままに引き受ける覚悟の姿である。他者から理解されることを放棄するのではなく、理解されないという現実に居場所を与える行為。それは、声にならないものに代わって、声を失わずに問いを発し続けるという行為でもある。
ハナの死は、誰にも代弁できない、私だけの現象であった。慰められることを拒否したのではない。慰めによって、あの死が誰にでも起こる普通の死に変えられてしまうことを恐れたのである。哲学とは、そうした「普通」の背後にひそむ痛みに名を与えずに見つめる営みである。
それでもなお、問い続けるしかない。なぜこの喪失は私を変えたのか。なぜ、愛するという行為は、癒しではなく痛みをもたらすのか。そして、なぜ私は、今もその痛みの中で、考えることをやめることができないのか。
哲学は孤独である。だが、その孤独こそが、痛みと共に生きる人間の誠実さである。