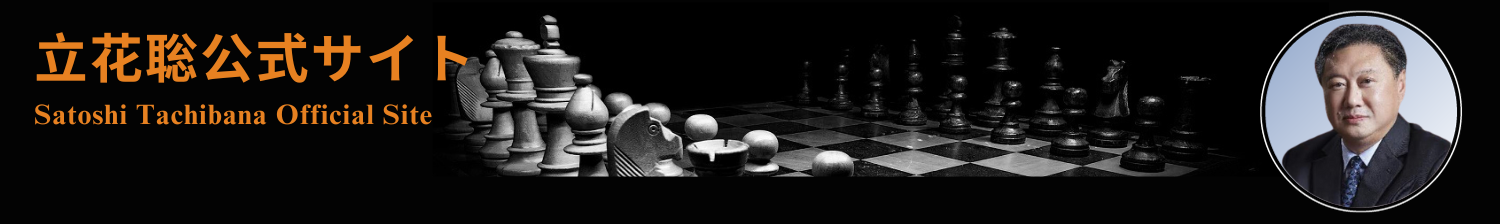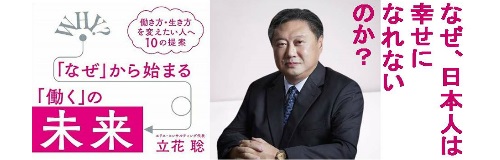【声明】本連載は、一般的なペット文化に親しんできた読者にとって、違和や反発を覚える内容を含んでいるかもしれない。私の価値観は、いわゆる一般通念とは明確に一線を画している。だがそれは、誰かを否定したいからではなく、動物と人間の関係において、装飾や従順性ではなく、存在そのものへの敬意こそが最も根本的であると信じるからである。この記録は、私と愛犬たちの静かな共生の記録であり、支配せず、飾らず、ただ受け入れるという、倫理的実践の記録でもある。
愛犬ハナが旅立ってから、私は彼女の生涯を記録する文章を綴ってきた。だが、ハナは特別な存在でありながら、同時に特別扱いしたわけではなかった。私が共に暮らしてきた4匹の犬たちすべてに対して、私は一貫して同じ接し方を貫いてきた――。
芸を教えない。衣装を着せない。飼い主の自己満足のために、写真映えのために、動物を飾らない。そこには単なる方針ではなく、明確な倫理観がある。

芸を教えることは、人間にとっては「かしこい」「かわいい」「誇らしい」という感情をもたらす。だが私は、「かしこい」「お利口」といった言葉そのものに、強い違和感を覚える。それらは、人間の知性を基準にして、動物の価値を測ろうとする視線の表出である。動物は、人間のような知性を持たない。だが私は、そこにこそ彼らの純潔の原点があると考える。
動物は、計算しない。疑わない。見返りを期待しない。だからこそ、彼らの忠誠は無垢であり、愛は打算を超えている。それは「知性の欠如」ではなく、むしろ「知性の超越」としての無垢さである。
これを「お利口」という言葉で評価することは、まるでその透明なまなざしに点数をつけるような行為に等しく、私はそのような発想に与することができない。人間には知性があるから、点数付けという評価を必要とする。動物はそうではない。
しばしば「犬も学ぶことを楽しんでいる」といった擁護論がなされる。だが、それは人間にとって都合のよい解釈であり、動物の内面や尊厳よりも、人間の安心や承認を優先させるものである。命は、何かを演じるために存在するのではない。自然のままに在ること、それをそのまま受け入れることこそが、人間にとって最も基本的な敬意である。
衣装についても同様である。ただしここで言う衣装とは、防寒や医療的必要性を除いた、装飾目的の衣装に限る。季節行事や記念日に合わせて、犬にコスチュームを着せ、写真を撮るという文化が広く見られるようになった。だがそれは、命のある存在を「イベント素材」に変えてしまう行為であり、動物を記号化し、人間の感情の消費対象に還元する視線の表れである。
私は一度として犬に装飾目的の衣装を着せたことがない。犬の毛並みと体温は、それ自体で完成された自然であり、美しさである。そこに人間の意匠を加える必要はない。むしろ、服を着せることで身体の自由や快適さを損ない、ストレスを与える場合すらある。
しつけもまた、必要最低限でよいと考えている。実際、私が飼ってきた犬たち―、特に野良出身の子たちは、人間の生活空間に自然に順応し、ほとんど教えることなくトイレや距離感を学び取っていった。それは「教えた」というより、彼らが観察し、判断し、共に暮らすという意志を持って応答した結果である。それこそが、支配ではなく、信頼に基づく共生である。
現代のペット文化は、「かわいくあること」「言うことを聞くこと」「写真映えすること」が評価の軸になっている。そのなかで、犬や猫は「存在」ではなく「演出された属性」として扱われがちである。だが私は、それに明確な違和を感じている。動物は、私たちの物語を飾るための存在ではない。彼らは、人間に対して沈黙の問いを投げかける倫理的他者である。
これらの問いを感知できるかどうかは、人それぞれの「感性」である。
愛犬ハナが見せてくれた忠誠、打算のない愛、静かな信義――それらは、芸や衣装や従順性の称賛といった表層の評価によっては捉えられないものだった。彼女は、ただそこに在ることによって、私に多くを教えてくれた。
私はその命を、飾らず、ねじ曲げず、ただ受け入れ、支え、見送った。
芸も、装飾目的の衣装も、「お利口」という称賛も、命を飾るものではない。命は、それ自体で完全である。この原点に立ち返ることが、動物と人間との真の共生への第一歩である私は信じている。