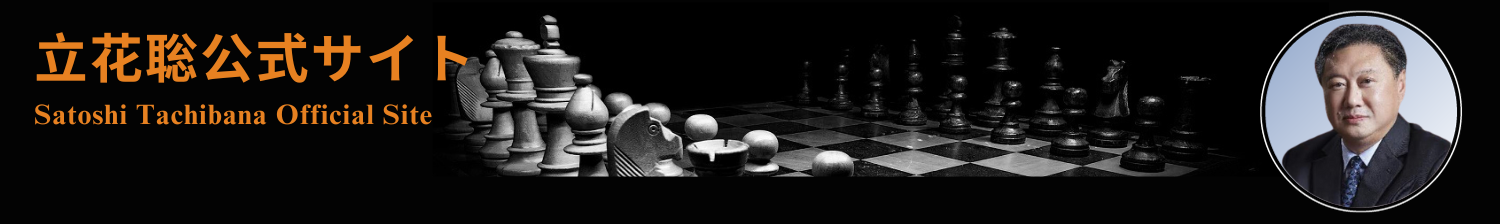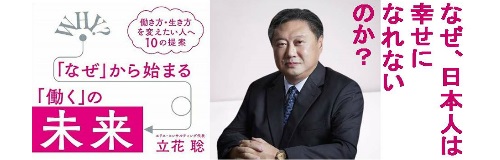東京大学教授阿古智子氏に対する反問と批判は、これで二度目だ。氏は自身のフェイスブックで「中国共産党と中国の人々を区別する」というが、まずは日本にいる中国共産党員と一般中国人をどう区別するか教えていただきたい。
中国共産党だって、日本軍国主義者と日本人民を区別すると言っている。幸い戦犯裁判があって辛うじて区別ができたことであろう。さあ中国共産党相手の裁判でもやろうか。浅薄だ。中国共産党の論法の焼き直しではないか。東大の先生ならもう少し上等な議論しようと。社会活動家、民主主義産業経営者として立派だが、学者としては落第だ。阿古先生の立ち位置は、中国共産党のプロパガンダの反対側にすぎない。
ちなみに東大に何人の中国共産党員がいるのか、ご存知でしょうか?阿古先生は区別して処遇してますか?もしや、東京大学に中国共産党支部が活動しているのかもしれない。どうしますか?先生。だが、氏のフェイスブックにコメントと質問をしても、回答はない。しかたないので、ChatGPTに聞いてみることにした。
大学の教授は、学者であり、学術の中立性を守るべきだと思うが、あえて特定の政治的立場やイデオロギーを前提にし、議論するのであれば、もはや社会活動家の範疇に入ると思われる。その辺の矛盾はどうだろうか?さらに仮説として、研究費や活動経費のような資金援助を特定の政治団体から拠出された場合の影響とは?このような、あくまでも一般論としてChatGPTに回答を求めたら、以下の回答が得られた。そのまま転載する(以下、ChatGPT回答)――。
● 学者の社会活動家化について
大学教授は学者であり、学術的中立性を守ることが求められている。学問の自由は、多様な視点から事象を分析し、独立した批判精神を持つことにその基礎がある。しかし、教授が特定の政治的立場やイデオロギーを前提にして議論を展開する場合、その行為は学問の領域を超え、社会活動家や政治運動の範疇に入ると言えよう。
ここに生じる矛盾は、学問の役割と公共的な役割の間にあるものである。学者は社会に影響を与える知識や見解を提供する責任があるが、その過程で個人的な信念が学術的中立性を侵害することがあれば、それは問題である。教授が自らの立場を強調して議論を進めるなら、その学問的信頼性が疑問視され、学生や学問そのものに悪影響を及ぼす可能性がある。
ただし、教授が個人的に特定の政治的信念を持つこと自体は問題ではない。しかし、それを講義や学術論文で押し付ける形で提示するのは、中立性の欠如と見なされるべきである。教授は、どのような信念であれ、それが学術的に十分に検証され、多様な視点から考察されることを心がける必要がある。学問の場では、批判的思考と多様な意見の尊重が不可欠であり、それこそが学問の真価である。
最終的に、学者が社会に対して果たすべき責任や、政治的信念と学術的中立性のバランスをどのように取るかは、それぞれの倫理観と学問的誠実さに委ねられる。学問の場が政治的プロパガンダに利用されることなく、真理の探求を目的とした自由な議論の場であり続けるべきという原則は揺るぎないものである。
● さらに学者への資金援助について
仮説として、特定の政治団体から資金援助を受けている大学教授がいる場合、学問の独立性や中立性に対する懸念が生じることは否定できない。研究費や講演料、執筆料、視察経費などの資金援助が提供されると、その教授が意図的あるいは無意識に、資金提供者の意向に沿った結果を出す方向に研究を進める可能性が出てくるからだ。
研究には独立性が不可欠であり、特定の団体や個人の利益を代弁するものであってはならない。しかし、資金提供者からの圧力や期待が強い場合、教授は「結果ありき」の研究を行うリスクにさらされる。つまり、研究の結論が予め設定され、その結論を支持するデータや分析のみが強調される形で研究が進められる危険性がある。
さらに、特定の政治団体や企業からの資金援助が公開されていない場合、研究の透明性や信頼性に疑問が生じる。もし援助が公表されていても、資金源が政治的に偏っていると見なされる場合、その教授や研究そのものが学問的価値を損なう恐れがある。
学術研究は本来、純粋な探究心に基づき、偏見や利害から自由であるべきだ。特定の団体からの資金援助がその原則を侵すような場合、学問の自由と中立性が脅かされ、結果として社会全体に対して誤った知見が広まる可能性がある。
このような状況を避けるためには、資金援助の透明性を確保し、研究の独立性を保証するための厳格な規制やガイドラインが必要である。学者は、自らの研究における利害関係を公表し、外部からの影響を最小限に抑える責任を持つべきである。それが果たされない限り、学問が政治や利害に操作される危険性は常に付きまとう。(以上、ChatGPT回答)