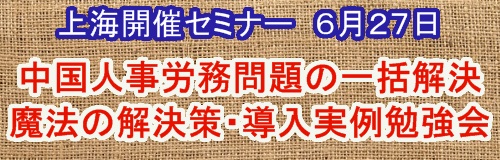体調が優れない。50代になると、病に少しでも侵され、苦しめられれば、死を思いつくのも不自然ではない。死を考えながらいつも、聴くのがマーラーの曲。
マーラーはつねに死を意識しながら、曲を書いていた。彼の交響曲、一曲一曲がすべて遺書のつもりで書いたのだろう。あれだけドラマ的な楽章を書ける天才は、オペラを書いた方がよかったのではないかとも思うが、でも、彼はオペラを残さなかった。
マーラー2番のフィナーレ、あの合唱――。
死を恐れるな!滅びを恐れるな!
生まれて来たものは、滅びなければならない。
滅び去ったものは、蘇らねばならない・・・
私は再び生きるために死ぬのだ!
蘇る、そう汝は蘇るのだ・・・。
マーラーの哲学は一部、ニーチェから引いているとも言われている。明らかに違う。「蘇るから、死を恐れるな」「蘇るために、死ぬのだ」という一見して、いかにもニーチェ風の哲学が綴られているが、やはり違う。あれはニーチェではない。
ニーチェが肯定しているのは、積極的ニヒリズム、それに基づく永劫回帰。ニーチェは主体的強さに価値を置いているが、マーラーが鳴らした天国の鐘は、やはり神の元での再生という他力本願的な弱さを示唆するものだ。
マーラー批判ではない。マーラーがどの神に身と再生を託しているのかだ。私は宗教を信じないが、神の存在を否定しない。ただ、それが自己超克によって存する自分自身の神でなければならない。
神に召還されるのではなく、自分の神を自分で召還し、自分の魂を最終的に託す。そこで果たして蘇るであろうとなかろうと、それは問題ではない。永遠の死という永遠の静寂をも喜んで迎え入れる。ニーチェの世界、「神は死んだ」と叫ぶツァラトゥストラのニヒリズムの本質はそこにある。
ということで、私は自己流の解釈に読み替えて、マーラーの曲を聴いているのである。