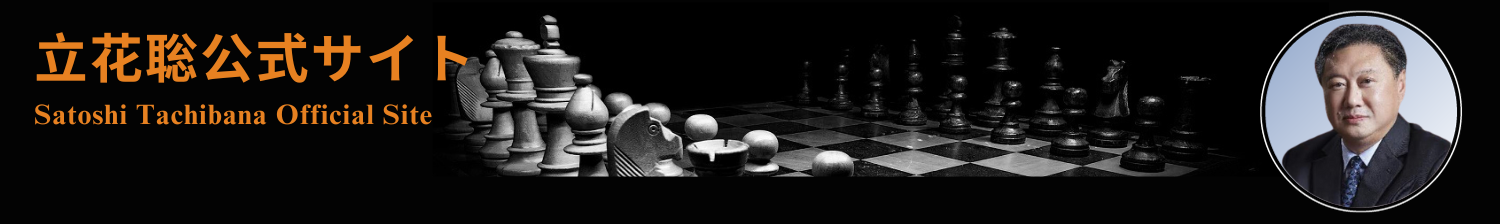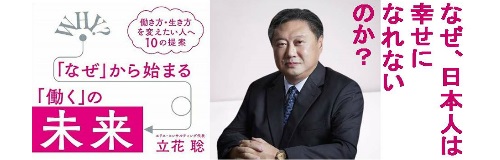我が母校・早稲田大学のサイトに、極めて示唆に富む研究報告が掲載されていた――。早稲田大学政治経済学術院の小林哲郎教授らの研究グループによるもので、タイトルは『日本人は権威主義国家のナラティブに広く説得されることが明らかに ― 民主主義国の主流ナラティブでは十分に対抗できない可能性 ―』である。
本研究の核心は、日本人が中国やロシアといった権威主義国家の「非自由主義的ナラティブ」に対し、民主主義国の主流ナラティブ以上に説得されやすい傾向がある、というものである。しかも、その影響は、政治的知識の多寡、陰謀論的傾向、権威主義的志向といった個人属性にかかわらず、広範に見られることが示された。
さらに、複数のナラティブを併せて提示する実験においても、非自由主義的ナラティブの影響が最後まで残る傾向が確認された。これは、SNSなどを通じて非自由主義的ナラティブが拡散される現代において、日本社会がいかに脆弱な状態にあるかを物語っている。
私自身、日頃からSNS上で「非民主主義のナラティブ」を積極的に発信してきた者の一人である。そして、私のナラティブは感情論ではなく、歴史的事実や統計的データに基づいて構成されている。
たとえば、先日私が投稿した「民主主義の導入によって政治的混乱や経済衰退、あるいは国家崩壊に至った国は数多く存在するが、民主主義導入によって真に繁栄した国は皆無に近い」という指摘は、あくまでも冷静な事実認識である。
このようなナラティブに多くの人が納得し、ときに自らの政治的立場や人生観を変えていった実例もある。では、なぜ民主主義の「正義性」が疑われると、多くの人は「なるほど」と反応するのか。その理由は、民主主義国家の教育とメディアが、あまりにも長きにわたって「正義としての民主主義」を教条的に刷り込み、代替的ナラティブの存在を排除してきたことにある。
この早稲田の研究は、その閉塞したナラティブ空間に風穴を開けるものである。すなわち、「自由・民主」を掲げる一元的な主流ナラティブの教育的・思想的支配に対し、非自由主義的ナラティブがいかに説得力を持ち得るかを、実験によって明確に示した点に価値がある。
逆説的にいえば、民主主義はその制度的価値ゆえに守られるのではなく、世論における説得力の競争を通じてしか維持され得ない。であるならば、民主主義国家がなすべきは、自らの正当性を声高に唱えることではなく、むしろ非自由主義的ナラティブの中にある一定の合理性・現実性と向き合い、それを凌駕する新しいストーリーテリングを構築することに他ならない。
民主主義そのものが虚構であるとまでは言わぬが、それを支えるナラティブがプロパガンダ化し、思考停止を助長するようであれば、もはやそれは信仰に過ぎず、教育ではない。本研究が明らかにしたのは、まさにその教育の欺瞞性であり、ナラティブ戦における構造的劣勢なのである。