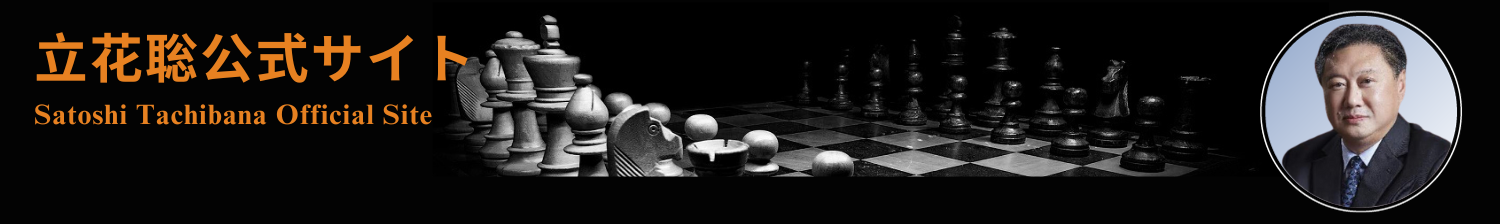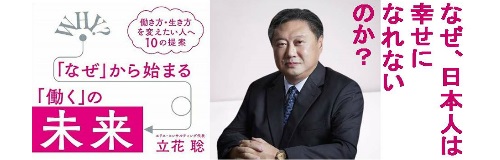最近、アメリカでも日本でも、社会全体にどこか独裁的なムードが漂っていると感じる人が増えてきた。「我々は民主主義国家ではなかったのか」「なぜ、いま独裁へと変質しつつあるのか」──そんな懸念を口にする声も少なくない。
しかし、この感覚は単なる不安や誤認ではない。事実、私たちは「変質」しているのではない。「回帰」しているのである。
言い換えれば、これまで塗り重ねられてきた「民主主義的な塗料」がゆっくりと剝がれ落ち、その下に隠れていた独裁の「正体」があらわになりつつある、ということだ。
● 民主主義の起源と機能――独裁の派生種としての民主制
民主主義とは、権威主義体制から自然発生的に対立して生まれたわけではない。それはむしろ、支配の正当化手段として進化した独裁の変種にすぎない。歴史を振り返れば、アテネの民主政は戦士階級の男性市民に限定された支配体制であり、フランス革命も共和政からナポレオンによる統領制(独裁)に急速に移行した。アメリカ建国の理想も、エリート層による制度設計に基づく利害調整の装置に過ぎず、いずれも「民意による支配」ではなく、「選挙という形式を用いた合法的統治」の確立を目的とした体制だった。
現代の民主主義もまた、本質的には「間接支配の制度化」であり、官僚、資本、メディアによって実権が握られている。国民の自由は制度の内側に管理され、「体制にとって無害な異論」だけが許容される。これはまさに、ミシェル・フーコーが語った「規律と管理による見えない権力の拡張」に他ならない。民主主義は自由の名のもとに、制度への従属を内面化させる装置として洗練されてきたのだ。
つまり、民主主義とは「独裁に見せかけない独裁」であり、「合法的に選ばれた独裁者による輪番統治」という逆説的構造に支えられてきた。カール・シュミットの言うように、「主権者とは、例外状態において決断する者」であるとすれば、民主国家における真の主権者は選挙民ではなく、非常時に「例外」を口実に秩序を支配する統治エリートである。
● 民主主義の構造的破綻と独裁への回帰
民主主義体制は、自由と寛容という理想を内在させながらも、その理想の無制限な拡張によって自壊の道をたどる。多様性と意見の相克、いわゆる国民の「分断」が制度の意思決定を麻痺させ、寛容が寛容を破壊し、自由が自律を失わせる。その結果、「決定できる強力な権威」への渇望が社会に蔓延する。
大衆は「自由」を求めるが、それは責任を伴わない快適な自由である。自らの判断で社会に参与する主体的市民ではなく、「導いてくれる誰か」に委ねたいという欲望を持った被支配者である。ハンナ・アーレントが『全体主義の起源』で描いたように、大衆は孤立し、思考停止した瞬間に「自発的な服従」へと滑り込む。独裁はそうした心理構造に即した支配形態であり、民衆の欲望に最も敏感に適応する。
このようにして、民主主義は自らが掲げるいわゆる自由と寛容によって内部から崩壊し、結果として原初的な権威主義形態への政治的回帰を遂げる。これは一時的な逸脱ではなく、構造的・歴史的な必然である。ここに「政治形態回帰の法則」が成立する。すなわち、すべての民主主義体制は、その自己矛盾と制度疲労の果てに、必ずや独裁的統治へと回帰する。
● 「民主 vs 独裁」の虚構――制度の名より実質を見よ
戦後世界は「自由民主主義 vs 独裁権威主義」という二項対立を正義の物語として内面化してきた。だがそれは、冷戦を正当化する地政学的プロパガンダであり、実態ではない。現実の体制運用においては、民主も独裁もともに管理・監視・統制の技術を進化させた支配装置である。
民主主義国家では、自由の名のもとに排除が行われ、同調圧力が制度化される。独裁国家では、支配の名のもとに制限が明示される。両者の違いは「何を目的に、どのように見せて支配するか」という演出形式の差にすぎない。
重要なのは、制度の名称ではなく、「誰が支配しているか」「どこまで支配されているか」「どのように正当化されているか」という実質である。民意と選挙の背後にあるのは、制度によって作られた「自由の型紙」であり、主権者としての人間はすでにそこに嵌め込まれている。
民主主義とは、独裁の否定ではなく、その戦術的擬態に過ぎない。そして今、その擬態の仮面が剝がれつつある。制度への信仰を棄てたとき、ようやく見えてくるのは、人間という存在が本質的に求める支配と服従の欲望、そして秩序の形式ではなく、力の分布と行使の構造である。制度に酔うな。見よ、誰が、どのように、君を黙らせるのかを。