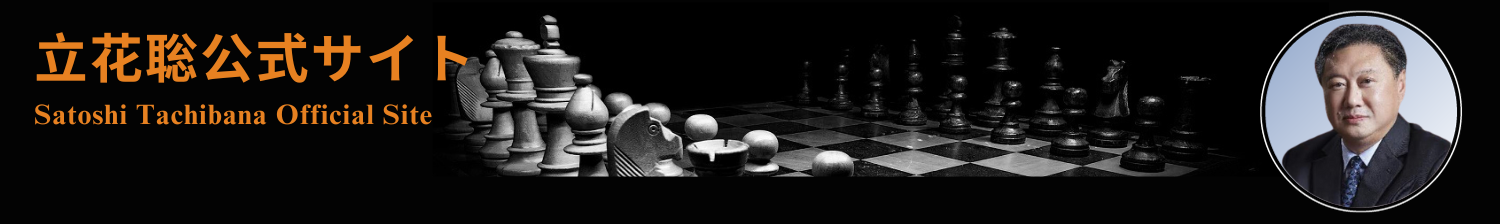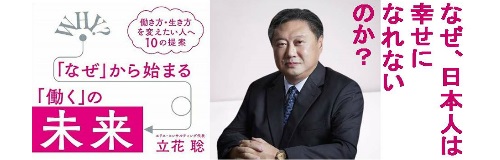日本維新の会の丸山穂高衆院議員の「北方領土を戦争で取り返す」発言(5月13日)で世論が騒然。最終的に党としては影響の拡大を避けるために、丸山氏に厳しい除名処分を決めた。この件は、拙稿「日本企業が『議論』を封殺する本当の理由」にも述べたように、「議論」次元の問題ではないかと考える。
● 問い方がまずかった
北方領土をロシアと戦争で取り返すのは賛成か反対か――。丸山氏が北方領土の元島民に投げた質問は、単純な質問として馬鹿げている。これに答えようがないからだ。
「戦争」という選択肢は、憲法上の規定もあり、日本人にとって基本的に取り得ない選択肢である。取り得ない手段の是非を人に問いかけても、相手を困らせるだけだ。現行憲法下で、「はい、戦争をしてでも北方領土を取り返そう」という答えは封印されている以上、タブーである。
一方、「領土を取り返す」という目的には異論を唱える余地がない。外国に不法占領されている我が国の固有領土を取り返すことは当然だ。この通り、目的が正しくても、手段が間違っていると、問題になる。しかも、この手段の間違いはちょっとした間違いではない。「戦争」という日本人がもっとも忌避している選択肢が持ち出され、まさに本質的な、受け入れ難い間違いだった。
丸山氏の質問を変えてみよう――。「もし、戦争が北方領土を取り返す唯一の手段だとすれば、北方領土を放棄するか」
問い方を変えることによって、雰囲気が一変する。まず「戦争」という手段をあくまでも仮説として打ち立てる。さらに論点は「領土を取り戻す」ではなく、「領土を放棄する」という対立面に置く。つまり、「戦争をするかしないか」よりも、「領土を取り戻すか放棄するか」の議論をしようということだ。
この問いかけを問題視することは難しい。もし問題視するなら、「戦争が北方領土を取り返す唯一の手段だ」という仮説に対して、「いや、戦争以外の手段もある」と、異なる仮説を打ち出す必要が生じる。これは建設的な議論になり、大変結構なことではなかろうか。
戦争以外の選択肢なら、話し合うことだ。いままで、日露両国がさんざん話し合ってきたが、まったく結実していない。なぜだろう。もしや「話し合い」の仕方がまずかったのではないか。ほかに何か良い話し合いの方法はないだろうか。と、議論が深まる。
● 「領土」が語られていない日本の憲法
侃々諤々の議論を交わした末、結果的にロシアといくら話し合っても、北方領土を返してくれないという結論に至った場合、武力や戦闘行為、あるいは戦争といった手段しか残らなくなる。
そこで、この結論(選択肢)を否定する現状(問題点)が浮かび上がる。それは戦争を否定する日本国憲法の存在である。では、「領土保全」という目的と「戦争」という手段の関係はどのようなものであろうか。
国家の成り立ちは、領域(領土・領水・領空)、人民(国民・住民)と主権という「国家三要素」に基づく。国際法上、これらの三要素を有するものは国家として認められるが、満たさないものは国家として認められない。法学・政治学においても一般的に、「国家の三要素」を持つものを「国家」とする。
しかし、「領土」の言及や規定は日本国憲法のどこにも存在しない。さらに日本の法律専門書を調べても、領土は国家の成り立ちとの関係で目立たないように論じられるものはあるが、領土保全の手段や諸要素の相互関連については、私の知る限り、立ち入った考察は多くなされていない。
隣国の中国は「領土」について、その憲法の前文にしっかり規定している。「台湾は、中華人民共和国の神聖な領土の一部である。祖国統一の大業を成し遂げることは、台湾の同胞を含む全中国人民の神聖な責務である」という明言があり、さらに、「主権と領土保全の相互尊重」などの5原則も掲げられている。故に、中国が台湾を武力統一するにあたり、その宣言であれ実施(侵攻などの軍事行動)であれ、少なくとも自国憲法上の根拠が存在するのである。
一方、日本の場合、この辺の関係は曖昧になっている。日本国憲法の前文には、「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意」と記され、さらに9条によって、戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認が宣言されている。では現実的に領土が外国に奪われた場合、戦争という選択肢は除外的にあり得るのか、明らかになっていない。
北方領土の現状を見ると、ロシアの支配・入植により、すでに日本人が住む場所ではなくなっている以上、「領土」という実感もそれを取り返す切迫感も薄れていることは否めない。では、情況を変えて、現在日本国の実効支配下に置かれているどこかの領土が他国に侵攻・占領された場合、日米安保条約に安心して委ねられるのだろうか。尖閣諸島について日米安保条約に基づく米国の対日防衛義務の適用対象になるかどうかでさえ、米政権の見解や認識の表明で一喜一憂しているのでは、話にならない。
北方領土を戦争でロシアから取り返すのは賛成か反対か、という趣旨の丸山氏の質問に対し、元島民の訪問団長が「戦争なんて言葉を使いたくない」と答えたところで、団長の内心の葛藤が浮き彫りになっていた。「戦争」という言葉を使いたくないからといって、領土の武力奪還を明確に否定したことにはならない。「領土を取り返す」という意思を放棄するといえば、論外であろう。
● 棍棒を持って、穏やかに話し合おう
「もし、戦争が北方領土を取り返す唯一の手段だとすれば、北方領土を放棄するか」という問いに変えられた場合、団長にとってさらなる残酷な「拷問」になりかねない。これを承知の上で、あえて私が提案したのは、どうしても、議論が必要だと考えたからだ。
前述した通り、法学的な「領土」の研究が少ないのは様々な理由があろうが、この探究は憲法学の専門家に譲りたい。しかし、領土問題は政治や外交上において実務的課題として常に存在している。その取扱いはどのような基準にすればいいのかという議論はもはや、先送りにできない、国家基盤にかかわる重要なアジェンダである。
丸山氏の質問方法は非常にまずかった。だが、その質問の趣旨が、領土保全の手段を問うところにあるとすれば、意義を否定できないものであろう。本人に対するある程度の処分はあってしかるべきだが、だからと言って、連座して提起された問題の本義を見逃したり、抹殺したりしてはならない。むしろこの際、丸山氏の間違った表現や質問方法と切り離して、いまだからこそ、この問題と堂々と向き合って議論すべきではないかと思う。
領土保全は、国家同士の力関係に依存している。ある意味で、戦争を放棄し防衛を他国任せにしている力の弱い日本はそもそも、軍事強国のロシアと同じ土俵にすら立てない。この現実を直視したうえで、まず対等に話し合えるためにも、日本自体の強化は欠かせない。これはすなわち安易に戦争という手段を講じるわけではない。この辺は、丸山氏の幼稚さが際立っていた。
「強化」とは、何か?
西アフリカにことわざがある。「Speak softly and carry a big stick, you will go far(大きな棍棒を持って、穏やかに話し合おう、それで言い分は通る)」。米国のルーズベルト大統領はこのことわざを借りて「Big Stick Diplomacy(棍棒外交)」を作り上げたわけだ。大きな棍棒は殴り合うためのものではない。穏やかに話し合って、言い分を通すための道具なのである。丸山氏は、「棍棒をもって殴り合う」ことを選択肢にした時点で間違っていたのである。
戦争もまた然り。「戦争ができる」ことと「戦争する」こととはまったく異なる概念だ。ある意味で「戦争ができる」という手段によって「戦争しない」「戦争を仕掛けられない」という「平和」目的を達成する。逆説的ではあるけれど。