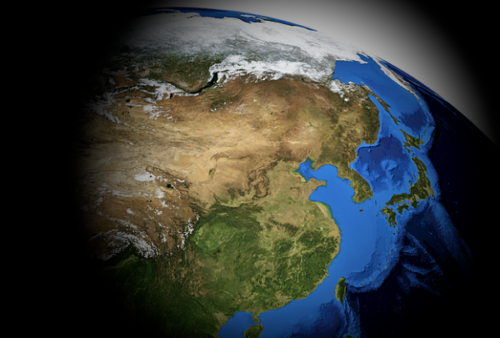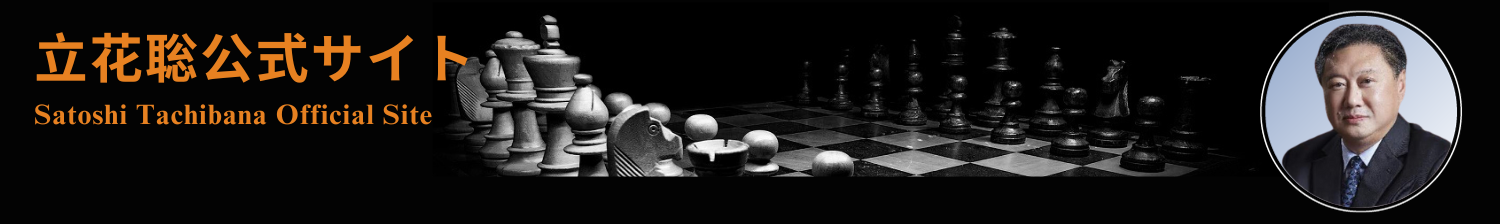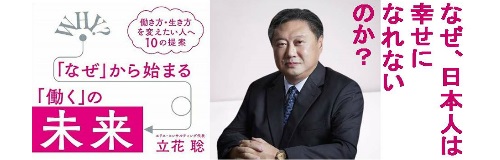● 批判しながら依存するという構造的矛盾
「旦那の浮気を批判しても、絶対に離婚しない“養われる妻”」。これは、私がよく使う比喩である。そしてこの一文こそ、現代の国際経済、とりわけ日本と中国の関係を説明する上で、極めて的確かつ本質的な洞察を提供する。
日本は「反中」的言説を繰り返しながらも、実際には中国のサプライチェーンに深く依存し続けている。製造業、物流、調達、価格競争力――そのいずれにおいても、中国なしでは成り立たない現実がある。だが、政治的には距離を置きたい。ここに、口では浮気を批判しながらも、生活の糧を絶たれる恐怖から離婚に踏み切れない「養われる妻」としての姿が重なる。
● 下部構造が上部構造を規定する――唯物史観からの視点
これは単なる皮肉ではない。極めて構造的な問題であり、マルクス主義的な唯物史観で説明することすらできる。すなわち、下部構造(経済的基盤)が上部構造(政治・思想・感情)を規定する、という理論だ。いくら「中国が嫌いだ」と感じ、口にしても、資材調達・価格競争・供給能力といった経済基盤が中国に握られている限り、国家としての“行動”は中国依存から脱却できない。これが現実である。
しかも厄介なことに、この「批判と依存の二重構造」は、日本に限らず多くの民主主義国家に共通して見られる現象だ。安全保障上のリスクや人権問題を声高に非難しながらも、実際の貿易量は増え続け、中国との経済的距離は縮まらない。これは道徳的な矛盾ではなく、構造的な合理性の表れであり、マルクスの言う「意識の虚偽(false consciousness)」の一形態でもある。
● 自立の意志と行動のギャップ――「産業回帰」の空虚さ
「産業回帰」や「国内回帰」が叫ばれて久しい。だが、実際に工場が戻ってきても、現場で働きたい日本人はどれほどいるのか。大卒偏重社会、現場労働の軽視、肉体労働忌避――いずれも“離婚したいが生活力がない妻”と同じ構造である。
いざ「自立せよ」と言われても、「え? 誰がやるの?」と尻込みする。結局、日本人の多くが「自分の手足で働く苦労」を避けたいがために、口では「中国に頼りたくない」と言いつつも、現実にはその供給網にしがみついているのである。
この乖離は、自己欺瞞に近い。現場に戻る覚悟もなく、依存を断つ努力もしないまま、「回帰」を語るのは空虚でしかない。
● 現実と向き合う構造的自己認識のすすめ
この構造の何が問題なのか。それは、批判する主体がいつまでも「養われる側」である限り、対等な関係を築けないという点にある。日本は「浮気する旦那」を批判しつつ、内心では「でもこの人がいないと生活ができない」と思っている“受動的パートナー”である。これでは、真の主権的経済運営などできるはずがない。
ではどうすればよいのか。「離婚するしかない」と単純に断じるのは現実離れしている。しかし、少なくとも「経済的に自立する努力」「選択肢を複線化する構想」「相手国との関係を交渉可能なレベルに戻す意志」が必要だろう。そのためには、まず現実を直視し、「自分たちは“養われている”のだ」という事実を認めることが出発点となる。
そして最後に、忘れてはならないのは、浮気する旦那=中国もまた「妻の生活の一部を担っている」限りにおいて、相互依存的であるという点だ。依存とは一方向ではなく、常に双方向的な構造である。この視点に立てば、日本は“見捨てられる側”ではなく、“交渉すべき立場”として再定義されるべきだ。
つまり、この比喩は「日本が情けない」という話ではない。「日本が何を見て、どう動くべきか」という構造的自己認識の提言である。口で何を言うかではなく、何に依存しているか。そこからしか、現実的な戦略は始まらない。