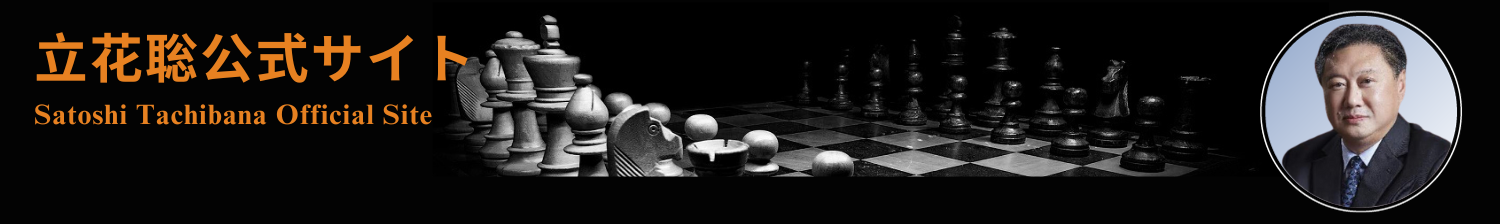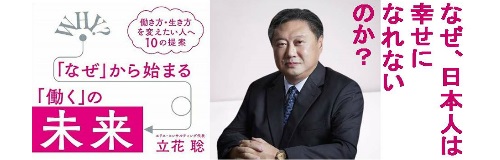上海で食べる「本邦菜(郷土料理)」。鱔(タウナギ)料理は欠かせない一品である。病みつきになるあの味は、夢にも出てくる。待ってましたよ、3年も。上海出張に先立って、友人の中国人弁護士が「歓迎の宴」を設けるから、食べたいものはと聞かれたら、厚かましくも響油鱔絲を頼んでみた。

淮揚名菜の響油鱔絲(鱔糊)。淮揚料理は、中国料理の四大ルーツの1つで、江蘇省の淮安市、揚州市、鎮江市を中心に、淮河と揚子江の下流域を取り囲む地域の土着の料理スタイルに由来する。これは、私の住むマレーシアにほとんど見ない料理部類で、どうしても上海出張中に食べておきたい。

タウナギは普通のウナギと比べると、肉付きが貧弱ゆえに食感も違う。普通のウナギなら、ふわっとした食感と良質な脂が口いっぱいに広がるが、タウナギは脂が少なく身質も硬い。そこで、素材の短所を「生かす」のが中華料理。淮揚料理ならではの濃厚な味付けで勝負する。「響油」という名は、炒めたタウナギの上に、ネギ、生姜、胡椒のみじん切りをのせ、スプーン1杯の沸騰した油を注いでジュワッとさせることを表現している。

タウナギは、単一素材の炒め物(清炒)のほかに、タケノコ炒めもある。それぞれ異なる食感でどれも捨てがたい。さらに鱔絲麺のように主食の麺の具材にもなる。上海滞在中に3度もタウナギのバリエーションを楽しんだ。もちろんどれも大満足。

中国語では、タウナギを「鱔」といい、ウナギの「鰻」と意図的に区別して使う。「鱔」とは「魚善し」で、もしや日本語の「鮨」のような含意があるのかなと、勝手に想像している。