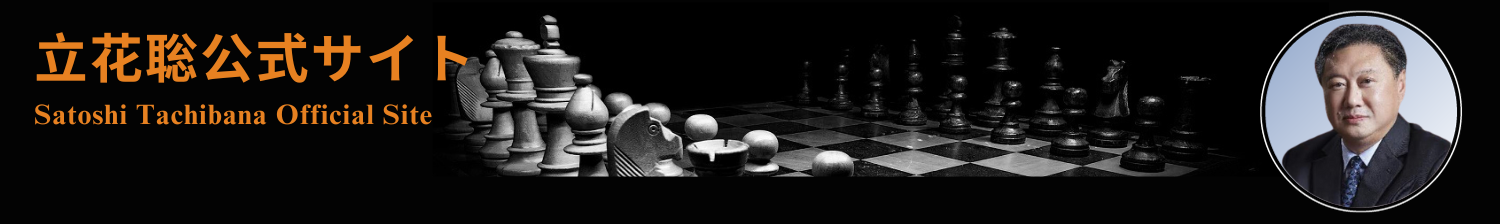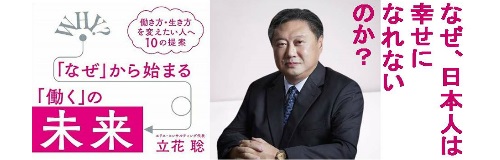● 色彩の変容と文化の再構築
かつて中国において、赤と白は厳然たる意味の分化を持っていた。赤は慶事を、白は弔事を象徴し、婚礼には赤、葬礼には白という使用区分は、儀礼的な秩序と価値体系の一部として受け継がれてきた。赤は繁栄、祝福、生命の象徴であり、白は死、喪失、無常の色として、社会生活に深く根付いていたのである。
ところが、現代都市部における結婚式では、白いウェディングドレスが主流となり、白は「清潔」「純粋」「高級感」の象徴として、祝儀空間に定着するに至った。それと対照的に、伝統的な赤は「レトロ」「土俗的」として周縁化され、家族儀礼や写真の演出要素にとどまる場合が多くなっている。
特に顕著なのは、家庭内で行われる「拝堂」(先祖や両親への礼拝)においては赤を基調とした伝統様式を守りながら、公共空間である式場では白を基調とした「式典」演出を採用するという、空間と機能による色彩の使い分けである。
家の内側では「孝」と「伝統」に支えられた内向きの礼儀が、赤を通じて表現される。他方、式場では「現代性」や「審美」が重視され、西洋化された白のドレスや装飾が標準となる。この使い分けは、伝統と現代、親族と社会、内と外という対照性を巧みに調和させるものである。
この色彩秩序の変容は、単なるファッションの流行ではなく、文化的意味の「再構成」であり、「伝統」から「商品」への変化、すなわち記号の再符号化(re-coding)に他ならない。赤と白はそれぞれ、新たな消費美学の中で再解釈され、装飾性やSNS映え、ブライダル産業の演出要素として再生産されているのである。
この現象は、伝統的価値観の喪失というよりも、むしろ文化の脱文脈化と再文脈化=「叙事化(narrativization)」のプロセスである。色はもはや感情や儀礼の根拠ではなく、「どのような物語に自分を位置づけたいか」を選ぶ記号になった。つまり、婚礼空間は単なる儀式の場ではなく、自己演出と社会的連帯の物語が演出される舞台なのである。
● 「ナラティブ」という武器――物語が支配の力となるとき
中国における紅白の婚礼の変容は、文化記号がいかに「叙事」の対象となるかの一端を示している。ここでいう叙事(ナラティブ)とは、単なるストーリーテリングではなく、記号に文脈と意味を与え、現実に秩序を与える知的操作のことである。
この「ナラティブ」という装置こそが、現代の統治や支配における中核的技術である。ニーチェが述べたように、「力で世界を変えられない者は、解釈で世界を変える」。つまり、解釈の力を持つ者こそが、現実の意味を支配するのである。だが、もし物理的な力をすでに握っている者が、さらに「ナラティブ」=意味付けの力をも手中にすればどうなるか。そこに成立するのは、「力に解釈、鬼に金棒」である。単なる暴力ではなく、正統性という幻想をまとった暴力=制度化された支配が成立するのだ。
現代の国家は、すでにこの段階に達している。民主主義であれ、独裁主義であれ、その体制は単なる制度ではなく、物語である。選挙制度があること、人民代表大会があること、それ自体は制度の存在を示すにすぎない。しかしその制度が「どう語られるか」によって、支配の正当性は決定される。中国の「全過程人民民主」も、アメリカの「自由と民主の砦」も、いずれも制度の記述ではなく、制度のナラティブである。
ゆえに、現代における支配とは、「物語を制する者が世界を制する」構造である。そして、このナラティブの技術は国家だけでなく、企業、教育、宗教、メディアに至るまで、あらゆる組織が競って獲得しようとしている。
記号が記号として意味を持たず、常に「どの物語に属するか」で価値を決定されるこの時代において、力なき者の抵抗は、意味を編むことから始まる。だが、もし力ある者が物語の意味さえも操作するのであれば、そこにあるのは、完全に構築された現実=物語の専制(narrative authoritarianism)である。